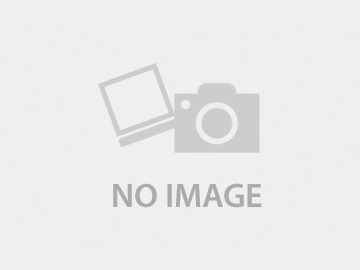中国経済停滞にチャンスとリスク見て取るG7各国-米欧でギャップも
記事を要約すると以下のとおり。
中国が経済的苦境に見舞われる現状にあって、米国をはじめとする主要7カ国(G7)にとっては、地政学的ライバルの中国に対する西側の立場を最終的に強化することになる根深い構造的問題の兆候を目にする機会が増えている。ボーイングの飛行機格納庫で記者会見したレモンド米商務長官(8月10日、上海)Photographer:QilaiShen/QilaiShen/QilaiShen/Bloomberg バイデン米大統領は8月30日、政治資金集めのイベントで、債務問題や人口動態といった長期的課題を理由に中国の経済問題は「時限爆弾」-辛辣な発言再び中国は「リスク高過ぎて投資できない」、米商務長官が企業の声を指摘中国景気のさらなる鈍化、世界中に波及の様相-身構える政策当局者中国経済を冷やす習政権の戦略転換-「日本化」シナリオに現実味バイデン氏、半導体など中国企業への米投資制限-大統領令に署名 ワシントンのシンクタンク、新アメリカ安全保障センター(CNAS)のリチャード・フォンテーヌ最高経営責任者(CEO)は「一般的な見解は中国の勢力の制止できない台頭を巡る懸念から、中国の経済および人口の取り返し不可能な落ち込みに関する心配に転じている様子だ」と話した。 これはバイデン政権内でひそかに広がりつつある見方だ。 レモンド商務長官の発言内容と同様、アデエモ米財務副長官は今週のブルームバーグとのインタビューで、「外国直接投資や外国企業にとって、中国の環境はあまり好ましくないものとなっているとの認識を示した。」一方で英国の場合、ディスインフレの弾みとなって物価抑制の取り組みを後押しするとして明るい兆しも感じられている。 米議会の米中経済安全保障審査委員会(USCC)はかつて超党派議員にとって中国台頭の影響を警告する場であったが、8月21日の公聴会で証言した民間部門のアナリストが伝えたメインテーマは中国経済の減速がどの程度続くのかは不透明だ。同国には景気を刺激して経済の崩壊を回避する財政力があると複数のG7当局者は指摘する。ブルームバーグ・エコノミクス(BE)のシニア地経学アナリスト、ジェラード・ディピッポ氏は、こうした困難でも中国当局が産業政策のために資金を投じるのが妨げられることはないとしても、政策の効果は落ちるだろうと分析した。BEの分析によれば、米経済はドル高も一因となってこのところ中国経済との差を広げ、この傾向は続く公算が大きい。 これらの当局者はまた、方針転換の必要性はまだ見当たらないと強調しつつも、センチメントの変化が西側の政策に影響し始めている兆候もある。 米当局者の1人が非公式に話したことろでは、敵対的な性格を強める中国自体の政策と同国の経済的緊張状態が、米国のいかなる制限措置で期待されるよりも対中投資を思いとどまらせる方向に作用しているとホワイトハウスは判断している。 当局者はまた、中国は引き続き多くの戦略的セクターで手ごわい課題であり、今後何年にわたってもそうあり続ける公算が大きいとしている。一つ目は「中国は豊かになる前に高齢化が進む」という点だが、それでも電気自動車(EV)のような「特定の戦略的産業に向けた中国当局の産業政策の取り組みの有効性」という、同じく重要なもう一つの要素の意義は減じることはほとんどないという。弱みを抱えても、中国は手ごわい経済的関係を深めており、新興5カ国(BRICS)が新たなメンバーに迎える国々のリストは新興国における中国の影響力拡大をあらためて浮き彫りにしている。このモデルは現在、少なくとも傷ついたと見受けられ、その魅力は薄れている。「欧州は中国から離れつつある」とコメントした。 イタリアはチャンスを見いだしている。 事情に詳しい複数の関係者によると、ロシアがウクライナでの戦争に気を取られている状況と相まって、中国の減速はイタリアにはプラスとなる一方ではないかという。 イタリア政府はまた、習主席が進める巨大経済圏構想「一帯一路」の投資協定について、離脱するかどうか年末までに決める必要があり、中国経済の減速はイタリアが関与を続ける論拠を弱める。 欧州は米国に比べ、引き続き中国を重商主義的な観点でみており、米欧の政策アプローチには常にギャップがある。ChineseTradeIsCriticallyImportantForTheWorldIt'sthetopexportdestinationfordistincteconomies. 英当局者は中国政府を経済的パートナーであると同時に国家安全保障上のリスクとして慎重にバランスを取っているが、英政府の考えに詳しい関係者1人の話では、中国の減速はG7で最も高水準かつ粘着的なインフレに悩む英国の抑制の取り組みを後押しするとして、おおむね歓迎すべきニュースと見なされている。 米国など各国の政策担当者およびその側近にとって重要な疑問は結局、中国経済の不振が一層好戦的な態度につながるのか、同国が協調的な姿勢になるかという、今後の展開だ。 サリバン補佐官をはじめとする多くのバイデン政権当局者は米中の2大経済大国間の対話継続の必要性と、米国の経済政策の新ビジョンを示した同氏のスピーチ草案策定にも携わったハリス氏は、中国経済の停滞が地政学的ボラティリティーが高まる方向に北京を駆り立てることも考えられると話す。 一方で、西側民主主義国が推進する経済モデルに代替するモデルを中国が売り込もうとする動きに打撃になるとして、中国経済の減速を比較的警戒しない見方や、中国指導部が国内の懸案に重点を置いて、世界的なステージでの自己主張が後退するとの予想もある。 CNASのフォンテーヌCEOは「中国は主要分野で強力かつ野心的であり続ける。」
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 中国経済停滞にチャンスとリスク見て取るG7各国-米欧でギャップも