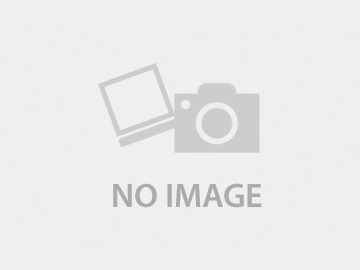政策正常化への植田日銀総裁の手法、「衝撃と畏怖」とは違うアプローチ
記事を要約すると以下のとおり。
4月に総裁が交代した日本銀行内では安堵(あんど)感がある。日本銀行本店Photographer:ToruHanai/Bloomberg 事情に詳しい複数の関係者らによれば、日銀総裁としては戦後初の学者出身である植田氏の学者らしいコミュニケーションの取り方が黒田氏は記者や政治家からの質問に対して詳細な説明をし、時にさまざまな角度から回答する特徴がある。だだ、こうした思考が植田氏にアイデアをもたらし、市場への影響を測るテストとして機能している。植田氏は、賃金と物価の好循環を見極めるのに十分な情報やデータが年内にそろう可能性もゼロではないことに言及しており、これはマイナス金利解除の可能性も-報道 事情に詳しい複数の関係者がブルームバーグに語ったところによると、総裁発言に関して日銀内では、従来と比べて踏み込んだ内容ではないと受け止められている。YCC政策は16年に黒田前総裁の下で導入された。 黒田、植田両氏をよく知る元日銀審議委員の桜井真氏は、「植田総裁は、投資家をパニックに陥れたり、住宅所有者や有権者、企業経営者が自身を総裁に任命した岸田文雄首相に反発したりするのを避けるため、正常化に向けた環境を水面下で構築している。」緩和の縮小ペースが遅過ぎれば円は安値を更新する可能性がある一方、急ぎ過ぎれば景気の腰を折り、デフレ不況を再び招く恐れがある。豪州やオランダ市場は日本の金利上昇に敏感日本からの証券投資エクスポージャー出所:ブルームバーグ、日本銀行 岸田首相が防衛力強化や少子化対策への支出増加を計画する中で金利が上がれば、債務の償還費や利払い費などの国債費がさらに膨らむ可能性がある。ブルームバーグ・エコノミクスの見方「植田総裁は論理的に話し、丁寧に質問に答えているが、戦略的なメッセージを送るという点では改善の余地がある。」バランスシート上の資産は日本の経済規模を25%上回る水準に達しており、米連邦準備制度理事会(FRB)や欧州中央銀行(ECB)と比べてもはるかに大きい。 植田総裁は、1990年代後半に日銀審議委員を務めていた当時から変わらず、物価と賃金、成長の好循環の実現に取り組む強い意志を示している。植田氏は経済の変化に合わせて政策を調整する能力を証明しているという。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 政策正常化への植田日銀総裁の手法、「衝撃と畏怖」とは違うアプローチ